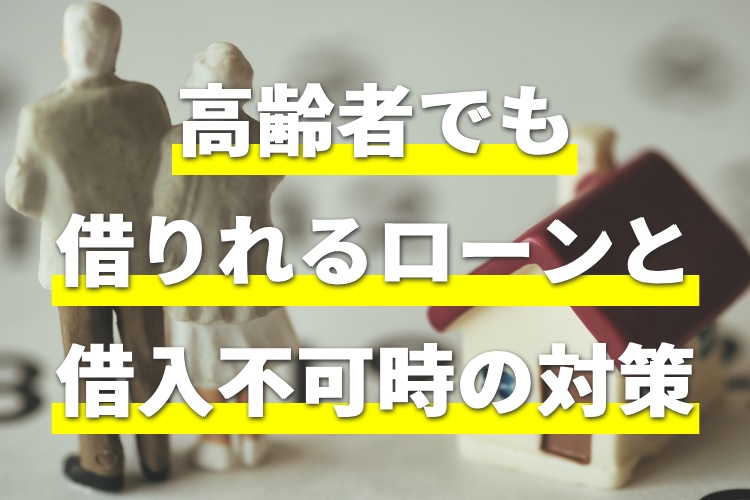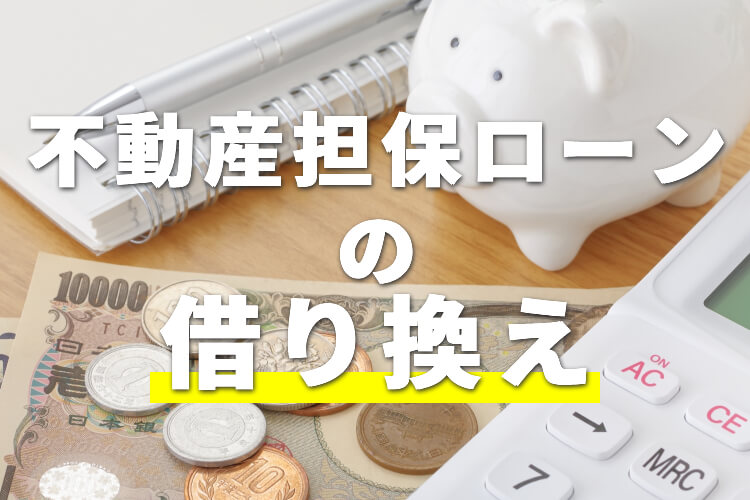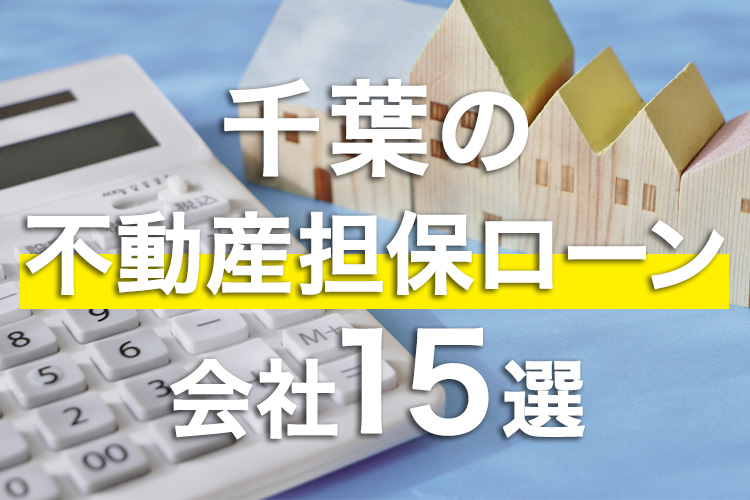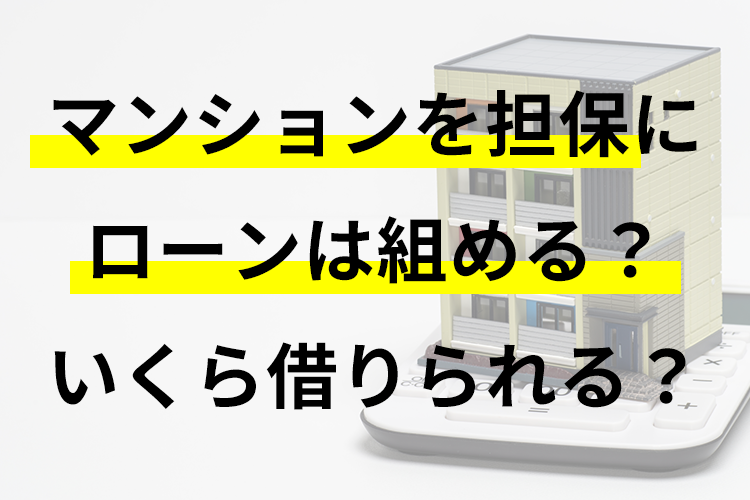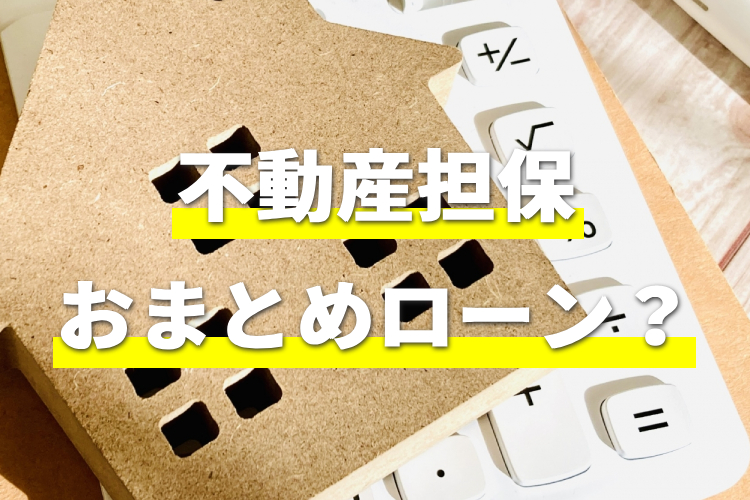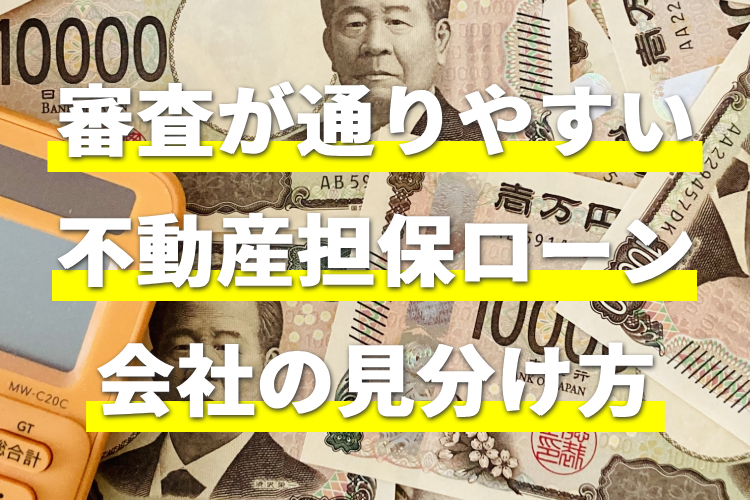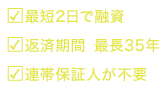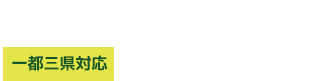「高齢者でも借りれるローンはある?」
「高齢者だからと借入を断られた…。他に方法は無いかな?」
このように考えていませんか?
この記事では、高齢者でも借りれるローンと断られた場合の対策について、プロが分かりやすくご案内します。
高齢者でも借りれるローンはあるが…
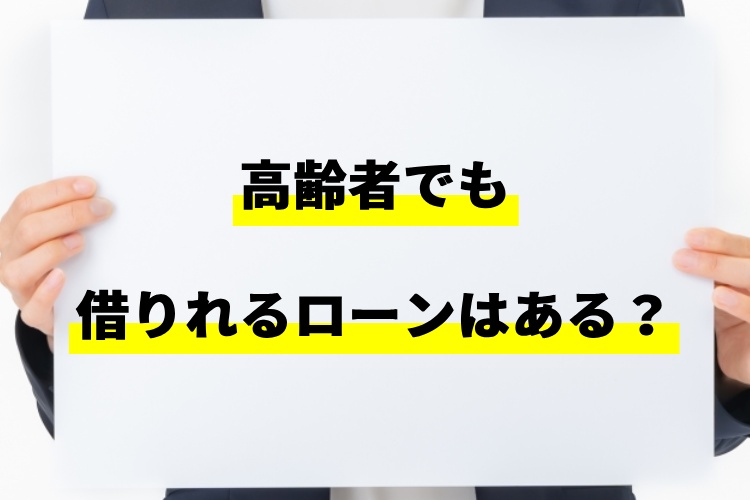
高齢者でも借りられるローンはあります。
※このページでは65歳以上の人を高齢者としています
ですが、年齢制限が設定されているローンは多いです。
その理由は、高齢者は収入が少なく、「返済不能になる可能性が高い(貸し倒れリスクが高い)」と金融機関が判断しているからです。
例えば、500万円を年利5%で借りた場合、返済期間によって、毎月の返済額は次のように異なります。
- 30年返済の場合:約 26,841円/月
- 10年返済の場合:約 53,033円/月
年金暮らしの70歳で上記の金額を返済し続けるのは、人によってはかなり厳しいはずです。
金融機関はこうした情報をもとに審査しています。
高齢者でも借りれる5つのローン
- ローンの種類
| 種類 | 年齢制限 |
|---|---|
| ①不動産担保ローン | 制限が無い金融機関がある |
| ②リバースモーゲージ | 60歳~80歳 |
| ③消費者金融のカードローン | 70歳未満 |
| ④銀行のカードローン | 70歳未満 |
| ⑤地方銀行のシニア向けローン | 75歳未満 |
「借りやすさ」「借りられる金額の多さ」「制限している年齢の高さ」を基準に、順番に5つのローンを掲載しています。
それぞれご案内します。
【種類①】不動産担保ローン
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対応している金融機関 | 銀行、信用金庫、信用組合、ノンバンク |
| 金利 | 年0.9%~15%程度(金融機関によって異なる) |
| 融資可能額 | 数十万円~数億円(土地の評価額の60~80%) |
不動産担保ローンとは、不動産を担保とすることで、お金を借りられる仕組みのことです。
ノンバンクでは、年齢制限を設けていないことが多いですが、銀行では、70歳以上の高齢者を対象外としているところが多いです。
金融機関による違いは次の通りです。
- 金融機関による違い
| 項目 | 銀行 | ノンバンク |
|---|---|---|
| 金利 | 低い | 銀行より高い |
| 融資可能額 | 数重万円~数億円 | 数重万円~数億円 |
| 審査のスピード | 1週間~ | 最短即日 |
| 審査 | 厳しい | 銀行より緩い |
| 年齢制限 | 70歳未満が多い | 制限がないケースが多い |
メリットは次の通りです。
- 自宅を売却せずに住み続けられる
- 土地の評価額の60〜80%の資金を借りられる
- 高額融資が可能
- 金利が低い
- 自宅や家族・親族の土地も担保にできる
仮に、家の評価が3,000万円の場合、1,800万円~2,400万円の融資を受けられる可能性があります。
デメリットは次の通りです。
- 不動産を失う可能性がある
- 諸費用がかかる
- 審査に時間がかかる
返済ができなくなると、金融機関が競売手続きを経て現金化します。
自宅を担保にする場合は、住む場所を失うリスクがあります。
高齢者もOKの会社を探す場合は、こちらの「ゆるいわけじゃないが、審査が通りやすい不動産担保ローン会社11社」をご覧ください。
【種類②】リバースモーゲージ
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対応している金融機関 | 大手銀行、地方銀行、信用金庫など |
| 金利 | 年3%前後 |
| 融資可能額 | 数十万円~数億円(土地の評価額の50~60%) |
リバースモーゲージとは、自宅を担保にして、老後資金を借りられるローンのことです。
生きている間は利息のみを返済し、死亡後に自宅を売却して元本を一括返済します。
契約時の年齢を60〜80歳と設定していることが多いです。
メリットは次の通りです。
- 自宅に住み続けながら資金を確保できる
- 土地の評価額の50〜60%の資金を借りられる
- 毎月の返済は利息のみで負担が軽い
仮に、家の評価が3,000万円の場合、1,500万円~1,800万円の融資を受けられる可能性があります。
デメリットは次の通りです。
- 自宅を失う可能性がある
- 相続人の同意が必要
- 地価下落により借入可能額が減る
- 資金不足になることがある
この他、夫婦の共有名義やエリア、構造制限で利用できない場合があります。
様々な制約や手続き、融資のスピードを考えると、不動産担保ローンの方がメリットが大きいです。
ただし、比較する点が多岐に渡りますので、金融機関に相談した上で、どうされるかをご判断ください。
【種類③】消費者金融のカードローン
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対応している金融機関 | 消費者金融 |
| 金利 | 年3%~18%程度 |
| 融資可能額 | 数万円~800万円 |
消費者金融のカードローンとは、最短即日で利用できる無担保ローンのことです。
多くの消費者金融は、申込み時の年齢を70歳未満としていますが、年金生活者でも申し込むことができます。
メリットは次の通りです。
- 即日融資が可能
- 保証人や担保が不要
デメリットは次の通りです。
- 金利が高い
- 総量規制の対象
総量規制とは、借り手の年収の3分の1を超える貸付を原則禁止とする貸金業法にもとづく制度です。
借入できる金額の上限の目安は、1年間で入ってくる年金の3分の1ということです。
金利は高いのですが、短期間で利用すれば、総返済額を少なくできます。
例えば、100万円を12%の利率で借りた場合、次のように異なります。
- 返済期間による返済額の違い
| 返済期間 | 毎月返済額 | 総返済額 | 利息総額 |
|---|---|---|---|
| 1年 | 88,486円 | 1,061,832円 | 61,832円 |
| 2年 | 47,088円 | 1,130,112円 | 130,112円 |
| 3年 | 32,134円 | 1,156,824円 | 156,824円 |
入ってくる年金を考えて、計画的にご利用ください。
【種類④】銀行のカードローン
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対応している金融機関 | 大手銀行、地方銀行 |
| 金利 | 年2%~14%程度 |
| 融資可能額 | 数万円~800万円 |
銀行のカードローンとは、銀行の個人向けローンのことです。
多くの銀行が、申込み時の年齢を70歳未満としています。
メリットは次の通りです。
- 消費者金融より低金利
- 即日~利用できる金融機関がある
- 総量規制の対象外
融資までの日数は銀行によって異なります。
デメリットは次の通りです。
- 審査が厳しい
- 融資に数日~かかる
総量規制の対象外ですが、銀行は返済が滞るような貸出しはしませんので、その面では安心です。
【種類⑤】銀行のシニア向けローン
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対応している金融機関 | 地方銀行、大手銀行 |
| 金利 | 年3%~14% |
| 融資可能額 | 数十万円~300万円 |
銀行のシニア向けローンとは、高齢者が利用できる地域限定の専用ローン商品のことです。
多くの地方銀行が、申込み時の年齢を75歳未満としています。
大手銀行にもシニア向けローンはありますが、地方銀行の方が充実しています。
メリットは次の通りです。
- 年齢制限が緩い
- 年金収入でも借りられる
- 総量規制の対象外
デメリットは次の通りです。
- 利用地域が限定的
- 借入上限が低い
総量規制の対象外ですが、銀行は返せる範囲の金額などを厳しく審査をします。
そのため、年金生活の場合は、借りられる金額は低めですし、断られることもあります。
最寄りの銀行に相談してみてください。
高齢者でも借りれるローンを断られた場合の5つの対策
それぞれご案内します。
【対策①】生活福祉資金貸付制度を利用する
生活福祉資金貸付制度とは、市区町村の社会福祉協議会が窓口となる無利子、もしくは低金利の公的融資制度のことです。
借入可能額や返済期間は資金の種類ごとに異なります。
- 資金の種類ごとの借入可能額と返済期間
| 資金の種類 | 借入金額 | 返済期間 |
|---|---|---|
| 総合支援資金 | 最大60万円 | 原則1年以内(最長2年) |
| 福祉資金 | 最大580万円 | 原則3年以内(状況により延長可) |
| 教育支援資金 | 入学費用最大50万円 | 原則10年以内 |
| 不動産担保型生活資金 | 最大月30万円 | 最長10年(状況により異なる) |
メリットは次の通りです。
- 無利子または低金利で借りられる
- 長期の返済期間が設けられている
- 用途に応じた借入が可能
デメリットは次の通りです。
- 審査に時間がかかることがある
- 借入可能額が低い制度が多い
- 連帯保証人が必要なケースでは、立てないと利息が発生する
あなたが利用できるのはどの資金なのか、最寄りの社会福祉協議会の窓口でご相談ください。
自宅など、担保にできる不動産がある場合は、不動産担保ローンを利用するとスピーディですし、多くの融資を受けられる可能性が高いです。
【対策②】生命保険契約者貸付を利用する
生命保険契約者貸付とは、契約中の生命保険の解約返戻金を担保にして、保険会社からお金を借りられる制度のことです。
借入可能額の目安は、解約返戻金の70%〜90%程度です。
メリットは次の通りです。
- 保険を解約せずに資金を確保できる
- 審査が不要で、信用情報に記録されない
- 任意のタイミングで返済できる
一括返済期限の設定がないため、任意のタイミングで返済できます。
デメリットは次の通りです。
- 借入額と利息が解約返戻金を超えると、保険が失効する可能性がある
- 未返済の貸付金があると、将来の保険金から差し引かれる
金利は年2%〜6%で、カードローンよりは低いです。
ただし、返済せずに長期間放置すると利息が積み重なり、解約返戻金が減ってしまいます。
生命保険に加入している方は、窓口にお問い合わせください。
【対策③】連帯保証人を立てて再申し込みする
「連帯保証人が必要」という理由で融資を断られた方は、安定した収入があるお子様やご親族に、依頼してみてください。
保証人がいる分、申込者の信用力が補完されるため、ローン審査に通りやすくなります。
メリットは次の通りです。
- 審査に通りやすくなる
- 保証人の分、借入上限が上がることがある
デメリットは次の通りです。
- 返済が滞ると保証人がリスクを負うことになる
- 家族や親族間でトラブルになるリスクがある
- 連帯保証人の同意を得るのが難しい
【対策④】不動産の売却を検討する
自宅や空き家を売却すれば、売却益が出ます。
メリットは次の通りです。
- 多額の現金を一括で得られる
- ローンの審査や返済負担が不要
デメリットは次の通りです。
- 住み替えが必要になる
- 査定や契約手続きに時間がかかる
売却価格の目安は、「路線価×土地の面積+建物の評価額」で算出できます。
ただし、売却時には税金や仲介手数料がかかりますし、住み替えのための費用がかかります。
不動産売却の会社と相談して、最終的にいくらが手元に残るかを把握してから、進めてください。
繰り返しになりますが、不動産がある場合は、スピーディでメリットの多い不動産担保ローンをご検討ください。
【対策⑤】生活保護の申請を検討する
生活保護とは、生活が困窮した場合に、最低限の生活費を国から受け取れる制度のことです。
支給額の目安は次の通りです。
- 高齢者の単身世帯で月約7万円~13万円程度
- 夫婦2人世帯で月約15万円~18万円程度
支給額は地域によって異なります。
生活保護を受けるには、次の条件を全て満たす必要があります。
- 収入が最低生活費に満たない
- 売却できる資産や貯金がない
- 親族から経済的な援助が見込めない
メリットは次の通りです。
- 無理なく生活を維持できる
- 医療費や介護費が一部支給対象になる
- 返済義務がない
デメリットは次の通りです。
- 自由に使えるわけではない
- 生活レベルや資産に関する制約がある
役所のケースワーカーが、遊興費(パチンコなどのギャンブル)や贅沢品の購入ではなく、生活費として使われているかをチェックしに来ます。
貯金もできません。
それでも、すべての手段が難しい場合は、「最後の支援策」として生活保護の申請を検討してください。
高齢者でも借りれるローンのまとめ
高齢者でも借りれるローンは複数ありますし、断られても、公的制度や不動産、生命保険を活用するといった選択肢があります。
ご自身の状況に合った選択肢を確認してださい。
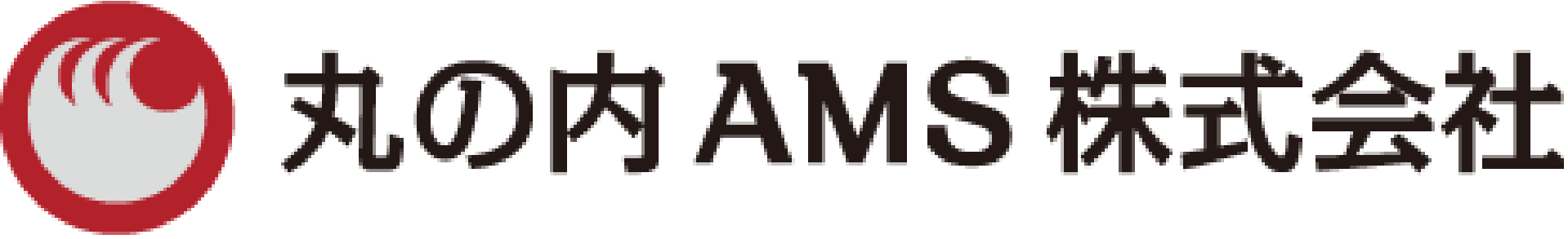
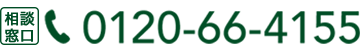

 不動産担保ローン
不動産担保ローン